目次
迫田ごうろの話・魔物の住むお堂・えんこうの恩返し・川底の地蔵・化け物問答・化け物退治
迫田ごうろの話し
井原の沢久(さわひさ)という部落(地図)にな、沢久という部落の山のこっちの一面がな、もう、こういうぐらいの石から上の石が全部集まってきてしまって、石ばっかりのところがある。ひどいものだ。『ごうろ』いうたら『河原』いう意味だがの。それを『迫田(さこた)ごうろ』いいよる。
川本の八谷(やたに)に善長寺(地図)という寺があるがな、昔、寺の釣鐘こしらえる時分に、鐘の材料として、世話人があちらこちらの田舎を回って、まぁいろいろな金(かね)を集めよった。そのときに、沢久の迫田ちゅぅ家にも寄って、大事にしておったおばあさんの鏡を、嫁さんだやら、誰だか知らんが、内緒でそれを寄付した。昔、婦人の持っとった手鏡な、あれ銅だけぇな。前のひらは、きれいにみがきさえすりゃぁ、こげやって、顔が映るようなものだがな。女の人は鏡は魂だといいよったが、それをお寺のことだからいうので相談もせず、寄付しんさった。
それからおばあさんが、帰って、わしが大事なあの鏡を寄付してくれた、というんで、怒って淵に身ぃ投げて、そしたら大きな蛇になって。
そいから、大風が吹くの、大雨が降るのして、沢久の山が、全部土砂崩れで抜けてしもうた。その部落の下にちょこっと狭いとこがあるが、あこが詰まって、水があっち越したちゅぅんだ。大変な岩ごうろが部落全体に流れ込んだ。
それで蛇がそれに乗って寺へいって、寄付した鐘へ巻きついて死んどったちゅぅ。その鐘にゃぁ、鏡くらいほどの穴が、ポカッとああとったそうだ。鐘は傷がついて鳴らんようになった。
和尚さんが椿の逆杭(さかぐい)をこさえて、蛇の頭に打ち込んで、お経を読み、呪文を唱えて、弔ったということだがの。
椿の逆杭ちゅぅのは椿の木を逆しい(逆さに)削った杭だがな。そのおばあさんの家が迫田(さこた)という家だった。それで、今もこう迫田ごうろいうて、一山、岩ばっかりの山がある。
二三年前に善長寺の沖ぃ、親類があるんだが、そこへ問うたが、
「その釣鐘はどがぁしただろうか」いうたら、
「今頃、寺の近くのお堂の下へいけて(埋めて)ある」いうてなぁ。
そいで、わしのおばあさんが、春の蓬を摘みにいくのに、そのお堂のほうまで行ったところが、
「そのお堂に近寄るなよ」いうて、部落のものらがのぅ、いいよったいうて。
何事だら知らんが、何だら呪いこんであるけぇ、いうことをいいよったそうだ。
(目次へ戻る)
魔物の住むお堂
ある夏の暑い日のこと、大きなけやきの下に立派な苧(お、麻)の蒸し場を作って、近所の人が寄り合って、男は、刈り取ったり、束ねたり、蒸す仕事をし、女は皮をはいで、乾かす仕事を受け持って、寄り合いで働いていた。
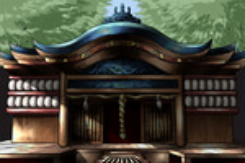 ある晩な、仕事が一段落したので、輪になって怪談をしておった。そのうち話は魔物の住むお堂の話になって、そのうちの一人が
ある晩な、仕事が一段落したので、輪になって怪談をしておった。そのうち話は魔物の住むお堂の話になって、そのうちの一人が
「今から、観音様におまいりしてくるちゅぅ勇気の人がおったら、わしのこの麻をみんなあげてもいいが」というた。そしたら、それにつれて、
「わしもあげる」というて言う。
するとそれを聞いとったお勝という女が
「そんなら、わしが行く」というて言うた。
お勝は、さっさと子供を背中に負うて、暗い外へ出かけていった。気丈なお勝は、観音様におまいりしたという証拠に、賽銭箱を抱えて、魔物の住むお堂にさしかかったところが、闇の中から
「お勝、待て」という声がした。
あの声は魔物の声に違いなかろう思うて、お勝は、振り向きもせず急いで、蒸し場へ戻ってきた。
そこにいたおばあさんが寂しかったろうと、子供をおろそうとしたんだが、手と足だけをだらりと下げた、赤ん坊の体があった。子供は、頭をもぎとられていた、という話だ。
(目次へ戻る)
えんこうの恩返し
昔のう、西の原のほうに、井原の西の原(地図)のほうに、古いお百姓さんがおっちゃったが、その家の前を小川が流れておった。そこへ土橋が架かっておった。道へでるには、いつもその土橋を通っておったんだが、ある晩のこと夢を見て
「わしは、おたくの前の土橋の下へ巣を作っておるえんこうですが、私のいうことをひとつ聞いてやんなさい」
「あぁ、そりゃぁ聞いてやろうが、どがぁいうことか」
 「実はあそこへ、何か恐ろしいものが、こう四つ股んなったものがでとります。あれがあるというと、もう身が震えるようで、そこ通るに通れんので、そのものが私の体にあたったら、私の体が腐りますので、ほで、私だけならええが、私の子供も傷つきますんで、ひとつそのものをどがぁぞして、取ってやんなさい」いうて、お願いしたそうだ。ほいして、
「実はあそこへ、何か恐ろしいものが、こう四つ股んなったものがでとります。あれがあるというと、もう身が震えるようで、そこ通るに通れんので、そのものが私の体にあたったら、私の体が腐りますので、ほで、私だけならええが、私の子供も傷つきますんで、ひとつそのものをどがぁぞして、取ってやんなさい」いうて、お願いしたそうだ。ほいして、
「その災いするものを取ってもらえりゃ、おたくがまっと(もっと)いつまでも栄えますように、お守りしましょう」いうて約束したそうだ。
「ほれ、なんでも夕べ夢を見て、こうこうこういうことだったが、お前はどう思うか」ちゅうぅて、朝ごはんのときにかかぁに話すと、
「ああ、そりゃぁ不思議な夢だが、そがぁなことがあるだろうか」、
ほいから前の土橋の下に行ってみると、まことそこに馬鍬(まぐわ)が置いてあったと、
「あぁはぁ、四股んなっとるものちゅぅものが、このことだな」
ほいで、そのものを取ってやったちゅぅんだ。そこへほっとたぁ(ほっといたら)腐るけぇ、まぁまぁよういうてくれた。知らせてくれたと思って、馬鍬持って帰った。その晩にまた、その、夢を見て、
「やれ、あれで楽になりました。で、夕べも約束しましたが、お宅の家をお守りしましょう」いうて、そいから、ずっとその家は幸せが続いたそうだ。
だけぇ、ああいうことは、自分のためだけじゃぁなぁ、人のことも考えて、物を置いたり扱うたりせにゃぁいけんけぇのぉ、いうことだ。
(目次へ戻る)
川底の地蔵
昔は小さい川を渡るのに、木を三本ぐらい、あっちとこっちと渡らして、その上を人間が歩く。牛や馬は草負い行くのに、橋の上はよう渡らんけぇ、川の中につながって、行きよった。
おじいさんが夜寝とられたら、地蔵さんが
 「川の底へ沈んどるが、毎日お前はここを通って、わしの頭の上を通って、草刈りに行ったり、薪こり(取り)に行ったりするんだが、わしを掘りあげてくれんか」言うて、枕上に(まくらがみに、枕元に)現れたそうだ。
「川の底へ沈んどるが、毎日お前はここを通って、わしの頭の上を通って、草刈りに行ったり、薪こり(取り)に行ったりするんだが、わしを掘りあげてくれんか」言うて、枕上に(まくらがみに、枕元に)現れたそうだ。
「こりゃぁ、不思議なことじゃ、川の底へお地蔵さんが沈んどりんさるいうこたぁ、うそか本当か知らんが、どうもわしにって、その仏さんが頼みんさるから、行って川を掘ってみる」いうて。
それで、川の底を掘ったら、お地蔵さんがなぁ、川の底から手も足も、こう皆ないようになっとって、顔のほうも傷だらけのお地蔵さんがでてきた。さてなぁ、一尺(30cm)ほどもあるだろうか。
お地蔵さんが今でもお祀りしてあるが。
(目次へ戻る)
化け物問答
昔、あるところの山奥に大変立派なお寺があった。そのお寺にゃぁ、いんげさん(和尚さん)がおられる。人々は、参拝して、仏さんの教えを聞かしてもろうて、戻っては畑仕事や山仕事にいそしんでおった。非常に穏やかな部落だったんだが、いつのほどよりか、お寺のお坊さんがおらんようになった。
なしておらんようになったんかわからん。お坊さんがおらんようになったんでは、仏さんの道を聞かしてもらうこともできんから、
「どっか、立派ないんげさんをやとうてくりゃぁええのう」いうて、新しいお坊さんをすえると、やっぱりいつのほどにか、そのお坊さんもおらんようになってしまう。
「わしゃ、おられん」いうて、逃げてしまいんさる。
どうもおらんようになる。なんぼやっても、おらんようになる。
「これじゃやれんのう」いうてみんないいよった。
 あるとき、お坊さんが一人通りかかって、日が暮れたもんじゃけぇ、
あるとき、お坊さんが一人通りかかって、日が暮れたもんじゃけぇ、
「あの奥に立派なお寺があるんだが、なして戸が立ってるんか(閉まっているのか)」いうた。
「お坊さんが長続きせんのですが、お坊さんが欲しいんだが、あんたもきちゃんさっただけぇの、何かの縁があるんだろうが、あのお寺へはいって、住職になっちゃんさって、いろいろ法話を聞かしてもらうことになっちゃりんさりゃぁ、よほどみんな喜びますがのう」ちゅうて。そしたところが、
「そりゃぁ、わしゃぁ、そのあちこちこう修行して歩く坊主だけぇ、そがぁなええ所があって、腰をおろさしてもらわれりゃぁ、いろいろな法話をしたり、そいから、あんたがたのご先祖の霊も供養さしてもらいますがのう」いうて、その坊さんが言うた。
ところが
「そりゃぁ、そがしちゃんさっても、いっそかまやしまいませんが、夜そのお寺へ泊まっちゃんさい」
「その寺へ泊まっちゃんさりゃ、夜中になっちゃ、いろいろ妖怪が出ていけんでありますが、まあ、それでそのお寺がもてんだけぇ」いうようなことを言い始めた。
そのお坊さんの言うことにゃ、
「そりゃ、まぁ、どういうことか知らんが、わしにひとつ泊まらしてみてくれ。わしゃ、ひとつ泊まってみるけ。どがぁな物が出るか知らんが、どがぁな物が出たとしたところで、わしは、まぁ、わしはわしなりの法の力で、そのものをなんとか鎮めてみせる。
そしてそのあとをやらしてもらわれることになりゃぁ、ここの住職になっていろいろ法を説いてみたい、そうなりゃ、みなさん参っちゃんさい」ちゅうた。
「そりゃ、そがぁしてもらいましょう」いうて、そのお坊さんは、その寺へ泊まった。
 泊まったところが、真夜中になって、天井のほうが、ガチャ、ガチャ、ガチャーっていうたり、せどの裏のほうが、ガチャ、ガチャ、ガチャーっていう。西のほうからもガチャ、ガチャ、ガチャーっという恐ろしい音がしたかと思うと、ま、人間じゃない、鬼のよう形をした、鼻も高い、目もつりあがって、光っとる、口も裂けとる妖怪が出てきて、仏壇におじぎをしたり、何かガチャ、ガチャいう。そうすると背戸の裏からも坊さんのような格好をした、妖怪が入ってきたのに向かって、
泊まったところが、真夜中になって、天井のほうが、ガチャ、ガチャ、ガチャーっていうたり、せどの裏のほうが、ガチャ、ガチャ、ガチャーっていう。西のほうからもガチャ、ガチャ、ガチャーっという恐ろしい音がしたかと思うと、ま、人間じゃない、鬼のよう形をした、鼻も高い、目もつりあがって、光っとる、口も裂けとる妖怪が出てきて、仏壇におじぎをしたり、何かガチャ、ガチャいう。そうすると背戸の裏からも坊さんのような格好をした、妖怪が入ってきたのに向かって、
「ちょっと、お前、遅かったじゃないか」
「いや、サイチクリンのケイゾウさん、ちょっと、わしはなぁ、その早うこう思ったんだが、くる途中で、お客にあってなぁ」
そうしたところが、東のほうから、稲光がして、大きな音がして、こんどは、ほうきに似た顔の妖怪が、入ってきた。
「テーテーこぶしさん、今晩、わしのところで、お産をせにゃならん人がおりましての、わしがいかなきゃぁ、そのもののお産ができんけえ、それで、来るのが、遅うなったけぇ」いうた。
そのものどもが、みな集まって、ごじゃごじゃ、ごじゃごじゃ、まあ、お経のようなことをして、夜が明ける頃に消えていった。何の災いもしゃせんけぇ、坊さんも無事だった。
あくる日の朝になって、
「夕べは、お坊さんが泊まりんさったが、まめじゃおりんさるやら、どがぁなことがあったやら」いうて、気づこうて、村の人がやってきた。坊さんは何の怪我もなく、息災で(無事で)おりんさる。
そのお坊さんは
「なんでも、不思議なことがあっての。サイチクリンのケイゾウだいうた。テーテーこぶしだいうた。ほうきの形をしたものもやってきた。これこれで、いろいろ妖怪が出たんだが、いっそ、何もわしに危害だけはせん。わしにまかせんさいや」という、
「そりゃ、まかせますが、どがしんさるか」
 ところがそのお坊さんのいうことにゃ、
ところがそのお坊さんのいうことにゃ、
「サイチクリンのケイゾウいうことは、サイは西、チクリンはたけばやし(竹林)、ケイゾウいうなぁ、鳥のことだ。
西竹林のケイゾウは、鳥の魂のことだ。あんたがたが、鳥をえっと落といて、西のほうの竹やぶに鳥の骨を捨てとろうが。鳥がよう成仏せん」
「テーテーこぶしいうもはなぁ、椿の木を切って、これを材料にした槌のことだ。椿の木の槌には、椿の木の精が残っとるから、それで仕事をしたものには、椿の霊が移って、迷うて出る。
普請やなんぞするときにゃぁ、椿を材料にして槌を作っちゃぁいけん。その槌の霊が、その家に宿る、その家にゃ、椿の精の妖怪が出る」いうようなことをいうた。
「家を掃除し、家を守るにゃ、箒を使う。ほうきの霊は女の人のお産やなんぞに立ちあわにゃならん。
ほうきをまたいだり、あっちこっちに投げ捨てたり、粗末にすりゃぁ、ほうきの霊がお産に立ち会うのが遅れる。難産をする」ちゅうようなことをお坊さんは言うた。
それから、お坊さんは部落の人をお寺へ集めて、今まで供養のとどこおっておった、いろいろな霊の供養をした。それで、そのお寺にも、いっそ、妖怪が出んようになった。
(目次へ戻る)
化物退治
ありゃぁなぁ、昔、石見の国に石見重太郎という強いお侍さんがおりんさったんだが、ある村へ出たときに、どこへ行っても、みんな戸を閉めて泣きよる。
 「どういうわけで泣くんか」いうた。
「どういうわけで泣くんか」いうた。
ところが、その村の人のいうことにゃ
「実は、この、三年に一度になるじゃぁあるが、祭りのあるときに、どこともなく弓の矢が飛んできて、一軒の家へ突き当たる。そいで、それがつき立ったときにゃぁ、その家の娘を、お宮の祭りの晩に、拝殿に持っていっとかにゃぁいけん。
生き餌(いきえ)としてさし上げにゃぁならん。そいで、その娘は、はぁ、戻りゃぁせん。村中のものが、よってたかって、まぁどうでもこうでも、その娘を、かごに入れて、その神さんへ供えにゃぁいけん。神さんの(が)そりょを取りんさるんだ。そいうことが今晩にあたるんだ」いうた。
それで、侍の言うのにゃぁ、
「そりゃぁ、何でもさえん(困った)ことだ。神さんちゅうものは人を守らにゃぁならんにかかわらず、人を取るちゅうことはない。そりゃぁ、神さんじゃぁないんだけぇ、わしがそのものを仕留めちゃろう思うけぇ。そいで、わしをその娘の代わりにしてくれんか」いうた。そいで、みんな
「そがぁしちゃんなさることなら、この上はないことだけぇ」いうて、
娘をさしださにゃぁならん家に当たった家にゃぁ、この上なぁその者を丁重に扱うて、ご馳走もして食わさした。
それでお侍さんは
「そいじゃぁ、わしはこれで行くけぇ。今までやりよった時のようにして、かごのなかに、娘の代わりにわしを入れて、夜、あこへおいとけ」いうた。
「そりゃぁ、そがぁしましょう」
村のものは、よってたかってお侍を連れていって、拝殿に置いた。
「早う帰らにゃぁやれんで。どがぁなものが出るだやら、わからんで」いうて、帰った。
お侍はいつどがぁなるやら思うて、かごの中へ入っとった。
「何ずが来たときにゃぁ、わしは弓でやっちゃろう」いうて弓を引きよった。
ところが、いつまでたっても、何のこともなぁ、夜は更けてくる。そのうち、真夜中になって、神さんの戸が、ギィーッて開いた。ギィーッて開いて、真夜中でわきゃぁわからんが、大きな目をしたものが、お侍の乗っとるかごのふたをガリッと引き破った。
あたりは真っ暗だけぇ、目の玉が光っとる。お侍はその光るものへ、矢を打った。そのものはギャーいうて逃げた。そいで、それぎり、まあ何のこともなく夜が明けた。
朝になったところが、血が落ちておって、それを尋ねていきゃぁええいうことで、それをたずねていったところが、大けな森に中に、大けな昔の木の切りがくい(切り株)があって、その下に、狒々(ひひ)が目をつかれて、死んでおった。
 「夕べは娘の代わりに、お侍がやられとるだろう。かわいそうなことをしたよのう。その代わりに娘が助かったるだが」いうて、村中のものが見ぃきた。ところがお侍は、その狒々を退治しとったんで、
「夕べは娘の代わりに、お侍がやられとるだろう。かわいそうなことをしたよのう。その代わりに娘が助かったるだが」いうて、村中のものが見ぃきた。ところがお侍は、その狒々を退治しとったんで、
「おぅ、こりゃぁ、まぁ化物を退治しとってだ」いうて、たまげた。
それ以後は、その村に、ああいうことはなくなった。そいで、今度は、そのお侍に
「あんたは、娘の命の恩人だけぇ、ここに止まって、どうぞ婿さんになってくれぇ」いうことをよほど(熱心に)頼んだ。
ところがお侍は、また、修行に出て行った、ちゅうようなことを聞いとるがな。
(目次へ戻る)